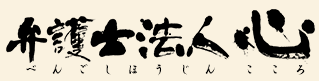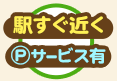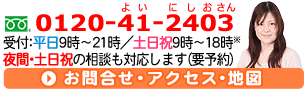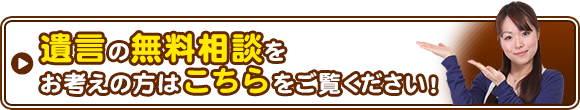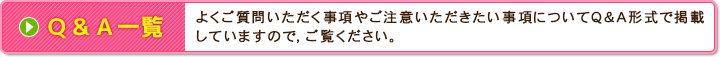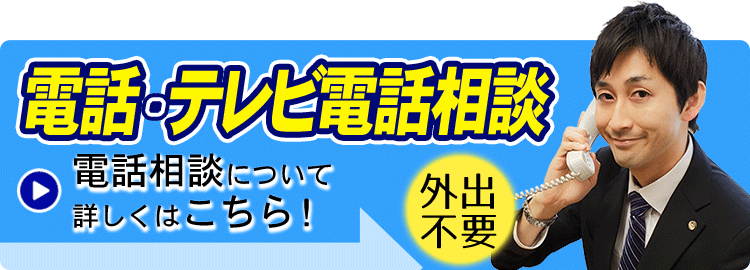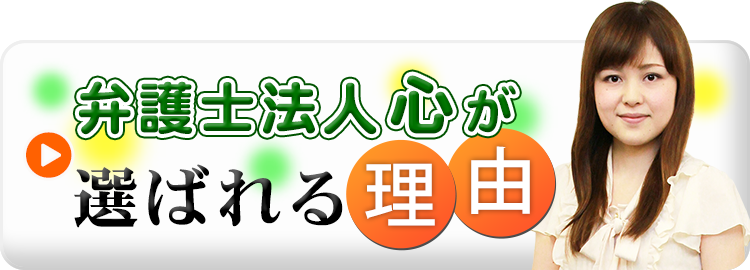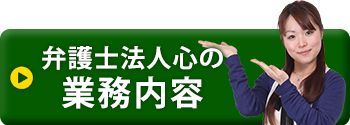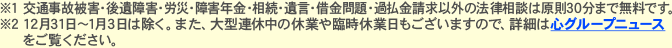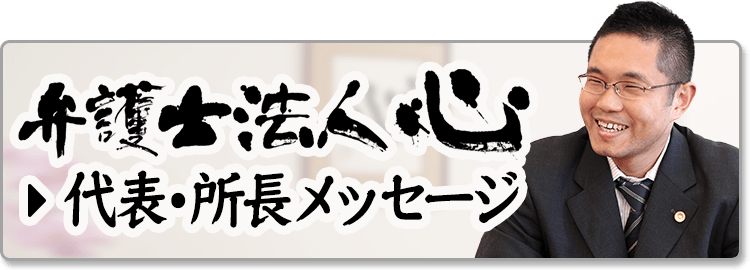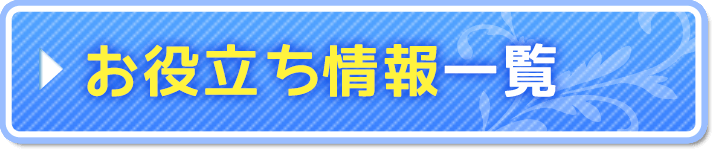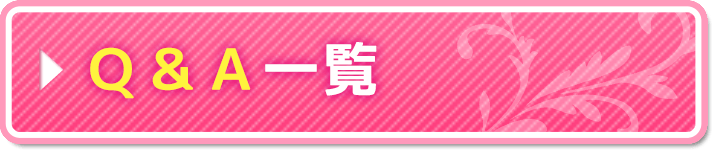遺言の検認手続きの流れと必要書類
1 自筆証書遺言は検認が必要
自筆証書遺言は、検認の手続きをする必要があります。
自筆証書遺言とは、遺言書を作成する方式の一つで、遺言者が自書して作成した遺言書のことです。
検認とは、相続人に対して、遺言が存在することやその内容を知らせるとともに、遺言書がどのような形状であったのか、訂正等の有無や内容、作成された日付、遺言者の署名など、裁判所において、遺言書の内容がどのようなものだったのかを明確にして、その後に遺言書が偽造や変造をされるのを防ぐ目的でなされるものです。
自筆証書遺言を保管する者は、遺言者が亡くなったことを知ってから、遅滞なく、家庭裁判所に検認を申し立てなければならないとされています。
自筆証書遺言は、検認の手続きをしなければ、不動産の名義変更や預貯金の解約などの相続手続きに利用することができません。
そのため、自筆証書遺言は、すみやかに、検認の手続きをしたうえで、相続手続きに利用する必要があります。
検認をしたことは、遺言書の効力には影響がなく、検認の手続きは、上記のとおり、遺言書の状態等を確認する手続きであって、遺言書の効力の有無を確認する手続きではありません。
検認の手続きは、相続人に通知されてなされますが、相続人が検認期日に参加することは検認の手続きの要件ではなく、相続人の全員が参加しなくても、遺言書の効力や検認の手続きに影響はありません。
なお、公正証書遺言や、法務局での遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認の手続きが不要ですので、注意しましょう。
2 検認の手続きの流れ
自筆証書遺言を保管している者は、必要な書類を準備したうえで、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。
どこの家庭裁判所に申し立ててもよいわけではなく、管轄の裁判所に申し立てる必要があります。
検認の管轄の裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所とされています。
たとえば、川崎市に最後の住所があった被相続人の遺言書は、横浜家庭裁判所川崎支部に申立てをする必要があります。
裁判所に検認を申し立てると、裁判所が検認の期日を指定し、相続人に対して、検認の期日の通知がされます。
遺言書を保管する者は、検認の期日に遺言書を持参し、裁判所が、立ち会った相続人らの前で、その内容を確認します。
遺言書が封をされているのであれば、裁判所がこれを開封しますので、遺言書を保管する者は、それまで開封してはいけません。
裁判所は、どのような状態で保管されているのか、相続人に対して遺言書の筆跡や印影は遺言者のものと考えるかどうかなどを質問し、その内容を調書に記載します。
検認がなされた遺言書は、その旨の記載がされたうえで、遺言書の保管者に返還されます。
相続人は、検認期日の調書の謄本を発行してもらうことができますので、それによって、どのような遺言書であったかを把握することができます。
そのため、検認期日に参加できなかった相続人も、この調書の謄本を発行してもらうことで、内容を把握することができますし、上記のとおり、検認の手続きは遺言書の効力に影響するわけではありませんので、無理に検認の期日に参加する必要はありません。
3 検認の手続きの必要書類
検認の手続きを申し立てるためには、その旨の申立書を提出する必要があります。
この申立書は、裁判所で書式が用意されていますので、それを利用して作成するのがよいでしょう。
申立書には、相続人を記載する必要もありますので、相続人が誰であるのかを確定しておく必要があります。
申立書に加えて、遺言者の相続人が誰であるのかを確定するための戸籍も提出が必要ですので、この内容を確認したうえで、申立書を作成するのがよいでしょう。
基本的には、遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人各自の現在の戸籍が必要です。
これに加えて、相続人が両親や兄弟姉妹であった場合、代襲相続が生じている場合には、これ以外の戸籍が必要になる場合があります。
検認の申立てには、800円の収入印紙の貼付と、相続人の数などに対応した郵便切手を提出することも必要です。
必要な郵便切手は、裁判所に確認をしたうえで、準備しましょう。